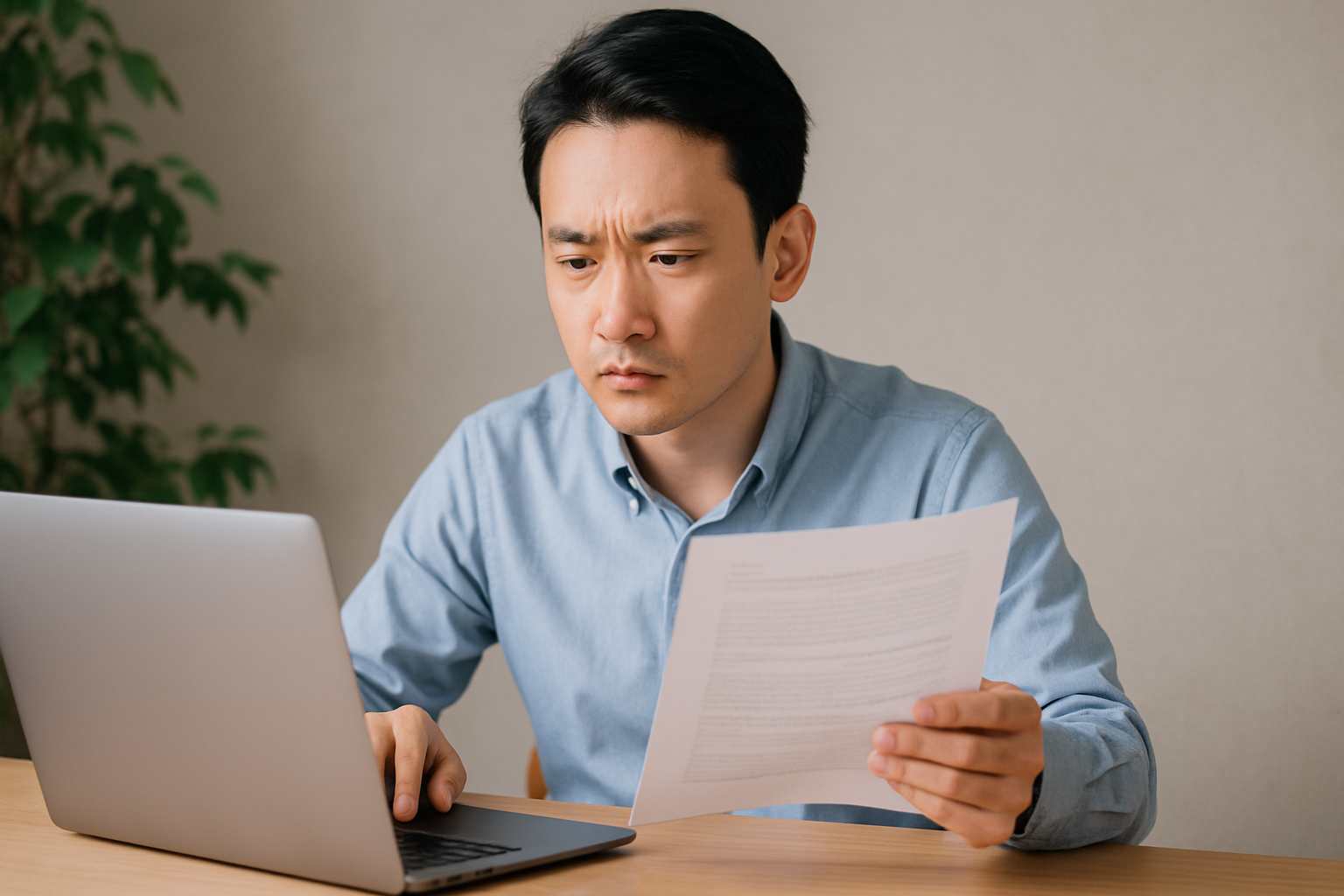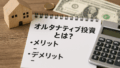副業の税金っていくらから?そんな疑問を持っていませんか?
「少しだけ稼いだだけでも税金ってかかるの?」「副業が会社にバレないか心配…」
そんなモヤモヤをスッキリ解消するために、この記事では副業にかかる税金のボーダーラインや申告のルールを、わかりやすく解説しています。
実際にいくらから税金がかかるのか、20万円の壁って何?住民税はどうなるの?など、初心者でもすぐに理解できる内容にまとめています。
さらに、バレずに副業をするコツや、節税テクニック、確定申告の手順まで、実践的なノウハウもぎゅっと凝縮!
この記事を読めば、「副業を始めていいのか不安…」という状態から、「これなら大丈夫!始めてみよう!」という気持ちに変わりますよ。
副業をこれから始めたい方、すでに始めているけれど税金のことが心配な方は、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。
副業の税金はいくらからかかる?知っておきたい基準
副業の税金はいくらからかかるのか?この疑問は、多くの人が副業を始める前に必ず気になるポイントですよね。
この記事では、実際に税金が発生する金額のラインや注意点について、わかりやすく解説していきます。
①副業の所得が年間20万円を超えた場合
副業の所得が年間20万円を超えた場合、原則として確定申告が必要になります。
ここで重要なのは、「収入」ではなく「所得」で判断されるという点です。
「所得」は、副業で得た収入から、経費を差し引いた金額を指します。
たとえば、副業で年間30万円の収入があり、10万円の経費がかかった場合、所得は20万円となります。
この20万円のラインを1円でも超えると、確定申告をしないと「無申告扱い」となってしまうため、注意が必要です。
なお、会社員の方が副業でこの基準を超えた場合でも、本業と副業の合算で税務署は判断しますので、特に申告ミスには気をつけましょう。
副業初心者にとって、この「20万円ルール」は基本中の基本。ぜひ覚えておいてくださいね。
②住民税は金額に関係なく申告が必要
住民税に関しては、所得が20万円以下でも申告が必要となるケースがあります。
これは自治体によって微妙に対応が異なることもありますが、原則として所得が発生している以上、住民税の申告義務があると考えておいた方が安心です。
たとえば、副業で15万円の所得があった場合、確定申告は不要でも、住民税の申告だけは求められることがあるのです。
また、申告しないままでいると、後から「副業がバレる」要因にもなってしまうので注意が必要です。
会社に副業がバレたくない人は、この住民税の取り扱いを特にしっかり管理することが大切ですよ~。
③アルバイトやパートは源泉徴収される
副業としてアルバイトやパートをする場合、給与という扱いになるため、源泉徴収が行われます。
つまり、収入からあらかじめ税金が天引きされている状態です。
この場合、給与支払者(雇い主)が税務署に対して申告を行っているので、自分で確定申告をしなくても済むことが多いです。
しかし、他の副業と合算して年間20万円を超えた場合には、自分で確定申告が必要になります。
また、アルバイト先が「扶養控除内」で収まるよう調整してくれているとは限らないので、年末調整がされていない場合には申告漏れの原因にもなります。
このあたり、少しややこしいですが、「自分で所得を管理する意識」を持つことがとても大事ですよ!
④副業の種類ごとに税金の扱いが異なる
副業にはさまざまな形態があり、それぞれ税金の取り扱いが異なります。
| 副業の種類 | 所得の種類 | 申告義務 |
|---|---|---|
| ライター・ブログ収入 | 雑所得 | 所得20万円超で確定申告必要 |
| アルバイト | 給与所得 | 給与支払先が源泉徴収、場合により確定申告 |
| フリマやハンドメイド販売 | 雑所得または事業所得 | 利益が出れば申告が必要 |
| 株式投資・仮想通貨 | 譲渡所得または雑所得 | 金額に関係なく確定申告の必要あり |
このように、どの副業で稼ぐかによって、税金がかかる「ライン」が変わってくるんです。
「どうせ少額だから大丈夫」と思わず、自分の副業がどのカテゴリーに分類されるのか、しっかり確認しましょうね!
⑤確定申告が必要なケースと不要なケース
以下のような場合は、確定申告が必要になります。
-
副業の所得が年間20万円を超えている
-
本業が年末調整されていない
-
複数の会社から給与を得ている
-
雑所得や事業所得がある
一方、確定申告が不要なケースはこちらです。
-
副業の所得が20万円以下(ただし住民税の申告は必要)
-
本業1社で年末調整済み
-
所得控除の変更などがない場合
このあたりの基準を知っておくだけで、かなり税務処理がラクになりますよ。
税務署に電話で相談するのも全然アリなので、不安があれば気軽に聞いてみてくださいね。
⑥無申告でバレた場合のリスク
「ちょっとぐらい…」と油断して申告しないでいると、副業がバレるリスクがあります。
バレる経路で多いのが、住民税通知と銀行口座の入金履歴です。
市役所からの住民税通知で、「本業と副業が別の課税額で表示される」と、会社の経理担当が気づくことも…。
また、メルカリなどの取引が銀行口座に記録されていると、税務署はそこから把握することもあります。
バレた場合、延滞税や過少申告加算税がかかるほか、最悪の場合には「税務調査」が入ることもあるんです。
きちんと申告しておけばトラブルは避けられるので、安心して副業を続けるためにも対策をしておきましょう!
⑦副業を始める前に準備したいこと
副業を始める前に、以下のような準備をしておくと安心です。
-
所得の管理方法(帳簿・アプリ)
-
開業届の提出(必要に応じて)
-
青色申告を検討する
-
経費として認められるものを知る
-
税金のための口座を分ける
これらを事前に整えておくことで、後から慌てずに済みます。
副業が軌道に乗ると収入も増えるかもしれません。
それをきっちり自分の武器にするために、税金の基礎を押さえておくといいですね。
副業の税金ラインを具体例でチェック
副業の税金ラインを、実際の金額ごとにシミュレーションして確認していきます。
どれくらい稼いだら税金が発生するのか、具体的な金額で見るとグッと理解が深まりますよ!
①副業で10万円稼いだ場合
副業で年間10万円の収入があった場合、基本的には確定申告は不要とされています。
ただし、これは「所得」が10万円である場合の話です。
たとえば、収入が10万円で経費がゼロなら、所得も10万円。
この場合、確定申告の義務はありませんが、住民税の申告は必要な可能性があるので注意が必要です。
また、住民税の通知から会社にバレる可能性もゼロではありません。
副業を内緒でやっている人は「住民税を普通徴収にする」手続きをしておくと安心ですね。
「少額だから」と油断せず、きちんとルールを知っておくことが大事ですよ~!
②副業で20万円稼いだ場合
20万円という数字は、税金の世界ではひとつのボーダーライン。
副業の所得がちょうど20万円であれば、ギリギリ確定申告は不要ということになります。
ただし、経費の申告ミスや勘違いで1円でもオーバーしてしまうと、申告義務が発生してしまいます。
たとえば、以下のようなケースは要注意。
| 副業収入 | 経費 | 所得 |
|---|---|---|
| 25万円 | 5万円 | 20万円 ← ギリOK |
| 25万円 | 4万円 | 21万円 ← NG(申告必要) |
また、繰り返しになりますが、住民税は別問題として考える必要があります。
住民税の申告を忘れると、副業がバレるリスクも高まりますので、申告の有無にかかわらず注意しておきましょう!
③副業で30万円稼いだ場合
副業で年間30万円稼いだ場合は、ほぼ間違いなく確定申告が必要になります。
特に、経費が10万円以内であれば、所得は20万円を超えるため、税務署への申告が必須となります。
このタイミングでおすすめしたいのが、「開業届の提出」と「青色申告の申請」です。
開業届を出せば、事業所得として扱うことができ、最大65万円の青色申告控除が適用される可能性があります。
たとえば、30万円の副業収入があっても、経費+青色控除で所得が0円になる、なんてケースも。
これ、めちゃくちゃお得なんですよ!
早めの準備で、税金を最小限に抑える工夫をしておくのがおすすめです。
④会社にバレない副業の税対策とは
副業でよくある悩みが、「会社にバレたくない…!」というもの。
その場合は、税金の手続きをちょっと工夫すれば、バレる確率をかなり減らせます。
ポイントは次のとおりです。
-
住民税を普通徴収にする(※確定申告書にチェック)
-
収入は個人口座ではなく、専用の口座を使う
-
SNSやネットで身元が分かる活動をしない
-
本名での取引を避ける(フリマなど)
特に重要なのが住民税の取り扱いです。
普通徴収を選ぶと、自宅に納付書が届くようになり、会社に通知されなくなります。
もちろん、完全にバレない保証はありませんが、きちんと対策すればリスクはグッと下がりますよ!
⑤開業届や青色申告のメリット
副業で年間20~30万円以上の所得があるなら、開業届を出すことを本気でおすすめします。
理由はシンプルで、税制上のメリットがめちゃくちゃ大きいからです!
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| 開業届 | 所得を「雑所得」から「事業所得」に変更できる |
| 青色申告 | 最大65万円の控除、赤字の繰越、家族への給与も経費にできる |
つまり、開業届を出して青色申告をすることで、
税金をぐっと抑えながら副業を続けられるようになるんです。
確かに、帳簿の記帳など手間は少し増えます。
でも、スマホアプリや会計ソフトが充実している今なら、初心者でもちゃんとできますよ!
副業が軌道に乗ってきたと感じたら、ぜひ検討してみてくださいね~!
副業の税金ルールを守って安心スタート!
副業の税金ルールをしっかり守っておくことで、会社にバレる不安や、あとから高額な追徴課税におびえることなく、安心して副業を楽しめるようになります。
ここでは、副業をスムーズに始めて、トラブルを回避するためのポイントをまとめました!
①確定申告の手順と必要書類
副業で確定申告が必要になった場合、まず流れを把握しておくと安心です。
確定申告の基本的な流れ:
-
所得をまとめる(収入-経費)
-
必要書類を用意する
-
e-Tax または紙で提出
-
納税(還付される場合もある)
主な必要書類は以下の通り:
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 源泉徴収票 | 本業の会社からもらう |
| 副業の収入明細 | 売上、振込記録など |
| 経費の領収書 | 消耗品、通信費など |
| 開業届(事業所得の場合) | 事前に提出済みが必要 |
| マイナンバーカード | 本人確認用 |
特に副業が「事業所得」として扱える場合は、帳簿の作成や仕訳も必要になってきます。
最近では、freee(フリー)やマネーフォワードクラウドなどの会計ソフトが充実していて、初心者でもスムーズに申告ができますよ。
申告時期(通常は2月16日〜3月15日)は混雑しやすいので、早めに準備を始めておくと安心です!
②税金を抑える節税テクニック
副業でも、ちゃんと節税のテクニックを活用することで、納税額をグッと抑えることができます。
特に、「事業所得」として申告できるかどうかが大きな分かれ目です。
節税ポイントはこちら👇
-
必要経費をきちんと記録・証明する
(通信費、電気代、道具代、レンタルスペースなど) -
自宅の一部を事務所として計上(家事按分)
-
青色申告特別控除(最大65万円)を使う
-
家族に手伝ってもらい、給与を払って経費に(専従者給与)
-
iDeCoやふるさと納税で所得控除を活用
要するに、「ルールの中で正しく税金を減らすこと」が節税です。
脱税とは違うので、きちんと記録していれば怖いことはありません。
毎月帳簿をつけておくと、確定申告時に慌てずに済みますよ!
③副業OKな会社とNGな会社の違い
実は「副業の可否」は会社ごとに違います。
最近は副業解禁の流れも強まってきましたが、就業規則に「禁止」と明記されている企業もまだまだあります。
副業のOK・NGを分けるポイント:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 就業規則 | 副業禁止が明記されているかどうか |
| 会社の許可制 | 申請すればOKの場合もある |
| 業務に支障が出るか | 勤務時間やパフォーマンスに影響する場合はNG |
| 利益相反 | 同業他社での副業は基本NG |
| 社外活動との関連性 | 本業と競合しないかがチェックされることも |
最近では、公務員も条件付きで副業が可能になってきています。
ただし、「バレないから大丈夫」と安易に考えず、事前に規則を確認しておくことが一番の安全策です。
もし心配なら、「匿名でできる副業」や「成果報酬型のフリーランス案件」など、会社に干渉されづらいスタイルを選ぶのもひとつの方法ですね!
まとめ
副業 税金 いくらから発生するのか?という疑問に対して、明確な基準は「年間20万円の所得」が目安になります。
ただし、住民税は金額に関係なく申告が必要な場合もあるため、「20万円以下だから安心」とは言い切れません。
副業の種類や収入形態によって、税金の扱いも変わるため、自分の副業が「雑所得」なのか「事業所得」なのかを把握することが大切です。
また、確定申告の際に「住民税を普通徴収にする」ことで、会社に副業がバレるリスクを減らすことも可能です。
節税や安心のためには、開業届の提出や青色申告の活用も検討すると良いでしょう。
副業を楽しみながら、税金の知識も身につけて、トラブルなく長く続けていけるようにしましょうね。